

メタバースゲームメディア
日本国内でメタバースについて専門的に学べる学校をご紹介!
近年、メタバースが注目を集める中、教育分野にもその影響が広がっています。
メタバース空間内でのバーチャルキャンパスの設置や、仮想空間内での取引やサービス提供のシミュレーションをカリキュラムの中に組み込んだ教育機関が日本国内で増えています。
その一方、メタバースについて専門的な人材を輩出すべく、全国の教育機関で専門学部や学科が新設されつつあります。本記事では、こうした専門学科を設けた学校や、その特色について紹介していきます。

目次
メタバース関連の大学
東京大学 工学部
東京大学の工学部は、日本国内外でトップレベルの教育と研究を提供する学術機関として知られています。
特に、近年急速に注目を集めているメタバースやバーチャルリアリティ(VR)、拡張現実(AR)といった分野では最先端の技術開発と研究が進められています。
工学部内の複数の学科で、メタバース関連技術を学べるカリキュラムが充実しており未来のデジタル社会を支えるための基盤となる技術を体系的に学ぶことが可能です。
東京大学工学部には、システム創成学科や情報工学科などメタバースに関連する知識やスキルを身につけることができる学科が複数存在します。
これらの学科では、コンピュータサイエンスや情報通信技術、VR・AR技術、3Dモデリング、データ解析、人工知能(AI)など、メタバースの構築に不可欠な技術領域を網羅的に学ぶことができます。
メタバース工学部
2022年7月には、上記の工学部や東京大学大学院工学系研究科が主体となり
メタバースの仮想空間内で構成された「バーチャル東大」内部に「メタバース工学部」が設立されました。
メタバース工学部は教育プログラムの一環で、実際に東京大学に進学せずとも参加することが可能です。
中高生やその保護者、教育従事者に向けた「ジュニア工学教育プログラム」と人工知能・起業家教育・次世代通信などの最新の工学や情報をオンラインで学ぶことのできる「リスキリング工学教育プログラム」があります。
(※「リスキリング工学教育プログラム」の受講は、現在は法人単位でのみ申込可能)
学べる内容
- VR・AR技術
メタバースの基盤となるバーチャルリアリティ(VR)と拡張現実(AR)の技術を学ぶことができます。
VRシステムの構築やARを活用した現実世界とのインタラクションについて網羅的に学べるのと同時に
3Dグラフィックスやコンピュータビジョンに関する講義や実験を通じて、視覚的な情報処理や仮想オブジェクトの生成・制御について、より深く理解することができます。
- シミュレーション技術
メタバース内での仮想環境の構築には、シミュレーション技術が不可欠です。
東京大学工学部では、物理シミュレーションや流体力学の知識を用いて仮想空間内でのリアルな物理現象の再現や現実的なインタラクションの設計方法を学びます。
これにより、仮想空間内のオブジェクトや環境を現実に基づき配置することのできるシステム設計が可能になります。
- 人工知能(AI)と機械学習
メタバース内での自動化や、自動学習システムの構築には、人工知能(AI)技術が重要です。
東京大学工学部では、機械学習やディープラーニングを用いたデータ解析技術を学び、仮想空間内でのユーザーの行動予測や、ユーザーが実際に対話していると錯覚するかのようなNPC(ノンプレイヤーキャラクター)を設計するスキルを習得することができます。より高度で没入感のあるメタバース体験の実現のために、不可欠な技術のひとつです。
- 3Dモデリングとコンピュータグラフィックス
メタバースの構築には、高度な3Dモデリング技術とグラフィックス技術が求められます。
東京大学工学部では、3Dデザインやアニメーション、テクスチャ生成など、コンピュータグラフィックス(CG)の理論と実践を学び、仮想空間内のオブジェクトやキャラクターのデザインスキルを習熟させることができます。
特に、リアルタイムレンダリングや光と影のシミュレーションといった先端技術を取り扱っているのが特徴のひとつです。
- ネットワークと通信技術
メタバースは、リアルタイムで多くのユーザーが同時にアクセスするため、安定したネットワークインフラと、高速なデータ通信が必要不可欠です。
東京大学工学部では、インターネット技術や分散システム、クラウドコンピューティングに関する知識を学び、メタバースの構築や運用に必要な通信技術の基盤を身に付けることができます。また、リアルタイムでの大規模データ処理や、低遅延ネットワーク技術についても学ぶことができます。
- ユーザーインターフェースと体験デザイン
メタバースの成功には、ユーザーが使いやすく、自然に操作できるインターフェースの設計が不可欠です。
東京大学工学部では、ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)の研究を通じてユーザーの行動や心理を考慮したインターフェースデザインや、
体験を最大化するためのユーザーフレンドリーな操作性の探求が、優秀な研究者たちのもとで絶えず行われています。
この環境下で学ぶことで、学生たちはより直感的で没入感のあるユーザー体験を実現するスキルを身に付けることができるようになるのです。
デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション学部
デジタルハリウッド大学は、「デジタルコミュニケーションを駆使して新たな創造にチャレンジする学びと実践の場」として創設された大学です。
デジタルコミュニケーション学部、デジタルコミュニケーション学科という「1学部1学科」で横断的にデジタルコミュニケーションを学ぶことが出来る独自のカリキュラムを提唱しています。
「専門教育」「教養教育」「国際教育」の3つの要素をカリキュラムの柱に据えており、
とりわけ「専門教育」領域における「VR/AR・メディアアート」分野については、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)など、
現実世界と仮想世界を融合して知覚する技術=XR(クロステック)や、
コンピューターや電子機器といったテクノロジーの力で人々の感覚を刺激する新しい芸術=メディアアートを複合的に学ぶことができる専門課程として設けられています。
学べる内容
- バーチャルリアリティ(VR)の基礎と応用
バーチャルリアリティ(VR)は、コンピュータ技術を用いて現実世界とは異なる仮想空間を生成しユーザーがその空間に没入する体験を提供する技術です。
このコースでは、まずVR技術の基礎として、3Dモデリングやリアルタイムレンダリング、視覚的な没入感を高めるためのインタラクションデザインなどを学びます。
応用編ではVR空間でのユーザー体験を高めるためユーザーがVRゴーグルを装着した際に直感的に操作できるインターフェースの設計や、VR空間内での物理的な制約を超えた体験ができるようなインタラクションデザインの手法(ジェスチャー認識やコントローラによる操作、視線追跡技術を利用したインターフェース)などが含まれます。
また、VRの技術を使って映画やゲーム、展示会などのインタラクティブなコンテンツを制作する実践的なスキルも養われます。
- 拡張現実(AR)の基礎と応用
拡張現実(AR)は、現実世界にデジタル情報を重ねて表示する技術です。
このコースでは、まずAR技術を利用して現実空間とデジタル情報が融合するような体験をデザインする方法を学びます。
ARは、スマートフォンやタブレットを通じて表示されることが多く日常生活の中で情報を効果的に伝えるツールとしても活用されています。
学生たちはUnityやARKit、ARCoreといったプラットフォームを使って、実際に動作するARコンテンツを開発する技術を学びます。現実空間の物体を認識し、それに対してデジタル情報を正確に重ね合わせるための技術やアルゴリズムも理解します。
応用編では、現実世界に情報を表示するためのアプリケーション開発や、広告や観光案内、エンターテインメントの分野での活用について考えます。学生は、現実空間に自然に溶け込むデジタルコンテンツ(ARを利用したゲームやアート作品、広告など)を設計し、それをどのように社会やビジネスで活用できるかを、実践的ワークショップを通じて学んでいきます。
- メディアアートの創作と表現技術
メディアアートは、デジタル技術を用いて視覚的、聴覚的な表現を行うアート形式でありVR/ARを使ったインタラクティブなアート作品(ユーザーの動きや声、触覚などに反応する体験型作品)の制作において、重要な役割を果たします。
デジタルハリウッド大学では、メディアアートの歴史や理論を学びながら、最新のデジタル技術を使って自分の創造性を表現する方法を習得します。
応用編では、公共空間や展示会などでのインスタレーション等のパブリックアートの制作を通じて、デジタルアートがどのように観衆と対話するかを学びます。
特に、ARやプロジェクションマッピング技術を活用した、都市空間での表現もこの領域に含まれています。
- クリエイティブプログラミング
VR/ARやメディアアートの制作には、プログラミングスキルが欠かせません。デジタルハリウッド大学では、クリエイティブプログラミングを通じて、アーティストやデザイナーが自分のアイデアを実現できるような技術を学びます。
学べる技術の一例としては、UnityやUnreal Engineなどのゲームエンジンを利用したVRやARのインタラクティブコンテンツのプログラミング技術が挙げられます。
これにより、アート作品やゲームのインタラクションをスムーズに実現するためのスキルを習得することができます。
またプログラミング技術を応用して、学生たちは自動生成アートの制作などにも取り組んでいます。
アルゴリズムを使って作品を生成する手法を学ぶことで、デジタルアートの新しい表現を探求することが可能になります
- プロジェクトベースの学習と実践
デジタルハリウッド大学では、学生が実践的なスキルを身に付けるためにプロジェクトベースの学習が中心的な役割を果たしています。
こうしたプロジェクトは、個人で行う場合もあればチームで協力して制作する場合もあり学生たちはこれらの協働作業を通じ、
リーダーシップやコミュニケーションスキルを培うこともできます。特に強調されているのが、共同制作のプロジェクトです。学生たちはチームを組み、各自が担当する役割に従ってプロジェクトを進行していきます。
例えば、ある学生が3Dモデリングを担当し別の学生がプログラミングを担当するなど、現場での実際の制作環境に近いプロセスを体験します。これにより、専門スキルを磨きながらも他の分野の知識も自然と習得することが可能となるのです。
プロジェクトは実際のビジネスやクリエイティブ業界で求められるスキルに直結しているため、
プロジェクト完了後には自分のポートフォリオとして活用することができ、就職活動にも大きな武器となります。
例えばVR/AR技術を使ったアート展示やゲーム開発、仮想空間でのインタラクティブコンテンツの制作など、制作物の種類は多岐にわたります。
このようなプロジェクトベースの学習は、単に技術を習得するだけでなく、プロジェクト管理や問題解決能力、チームワークといったソフトスキルも身に付ける機会を提供します。
これにより、学生は卒業後VR/AR開発やデジタルアート、ゲーム業界などで即戦力として活躍できる人材へと成長します。
実際に手を動かし、試行錯誤しながら作品を作り上げるプロセスが、現場での実践力につながるのです。
■開発を検討されている方は気軽にお問い合わせください
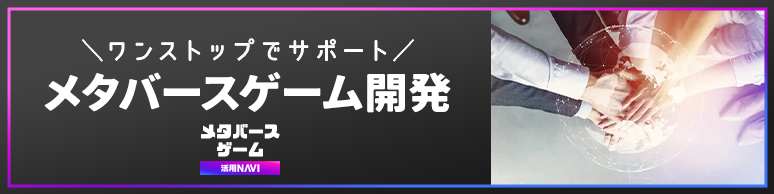
メタバース関連の高等学校

N高等学校・S高等学校
N高等学校およびS高等学校(以下、N高・S高)は、学校法人角川ドワンゴ学園が運営する通信制の高等学校です。
2016年に設立されたN高は、これまでの通信制高校の概念を一新し、IT技術を駆使した教育プログラムを提供することで注目を集めています。
S高はN高の姉妹校として2021年に開校し、N高と同様のデジタル教育を提供しています。
また、2025年4月には、さらなる姉妹校としてR高等学校の設立も決定しています。
これらの学校は、場所や時間に縛られず自宅などの好きな場所からインターネットを通じて学べる環境を整えており、これまでの通信制高校と比べて、より柔軟で充実した学びが特徴です。
N高・S高は、日本全国だけでなく海外在住の生徒にも対応しており世界中どこからでもオンラインで授業を受けることが可能です。
また、進学やキャリア支援にも力を入れており、大学進学コースやプログラミング、デザインなど専門スキルを学ぶコースも充実しています。
両校の魅力は、学生が自分のペースで学べるオンライン教育だけでなく、学生同士の交流やイベントが積極的に行われる「バーチャルキャンパス」や「メタバース教育」にあります。これにより、全国どこにいても、リアルタイムで友人や先生と繋がりながら学ぶことができ、学校生活をデジタル空間内で体験できます。
学べる内容
N高・S高で学ぶことのできるメタバース教育の主な特徴は、以下の通りです。
- バーチャルキャンパスでの学び
N高・S高では、メタバース空間内にバーチャルキャンパスを展開しています。このキャンパスでは、仮想空間を利用して、生徒が各自のアバターを用いて、授業や校内行事に参加することが可能です。仮想空間の中で、生徒たちは実際の教室にいるかのようにリアルタイムで授業を受けることができ、他の生徒や教師ともコミュニケーションを取ることができます。
バーチャルキャンパス内では文化祭などの校内行事やクラブ活動なども活発に行われており、従来のオンライン学習以上に、学校生活の一体感を体験することができます。
- VRやAR技術の基礎
メタバース空間を理解し構築するには、VR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)の技術が不可欠です。
N高・S高では、これらの技術の基礎を学び、実際に仮想空間を作成・運用していくためのスキルを習得することができます。
具体的には、VRシステムの構築やAR技術を活用したデジタルコンテンツの制作方法仮想空間でのインタラクション設計について学ぶことができます。
これにより、生徒はメタバースの技術的な側面を理解し将来の応用に向けた基礎力を養うことが可能となります。
- プログラミングとデジタルコンテンツ制作
メタバースを運営するには、プログラミングやデジタルコンテンツの制作が重要です。
N高・S高では、プログラミング教育に力を入れており特にメタバースでの応用を意識したプログラミングスキルが特徴です。
両校の生徒たちは、3Dモデルの制作やアニメーション、ゲームデザインさらにはインタラクティブな仮想空間を設計するスキルを身につけ一般的な高校生の水準以上にデジタルコンテンツについて習熟し自らそれらのコンテンツを制作できるようになります。
- メタバースでの社会参加やビジネスの学び
両校のメタバース教育では、仮想空間内での社会参加やビジネス活動について学ぶ機会も設けられています。
このカリキュラムには、仮想空間内での経済活動やマーケティングの基本的な知識なども含まれています。
生徒たちは、仮想空間内での取引やサービス提供のシミュレーションを通じてメタバース経済の仕組みや将来的なビジネスチャンスを理解することができます。
生徒たちはこの過程で、デジタル技術だけでなく実際のビジネスにも応用できる実践的なスキルを習得することができるようになるのです。
日本航空高等学校 メタバース工学科
日本航空高等学校は、航空業界での活躍を目指す学生を育成するための専門的な教育を提供している学校として有名ですが、
近年では新たな技術分野にも注目し、教育の幅を広げています。
その一環として、同校は2024年4月から通信制課程に「メタバース工学科」を開設し次世代のデジタル技術を学ぶ環境を整備したことで大きな反響を呼びました。
メタバース工学科では、急速に発展するデジタル空間「メタバース」の構築に必要なスキルや知識を学ぶことができます。
仮想現実(VR)や拡張現実(AR)といった技術を基盤にデジタル空間でのコミュニケーションやビジネス、エンターテイメントが展開されるメタバースは、これからの時代の新しい経済圏や社会の形態のひとつとして、注目されている分野です。
日本航空高等学校のメタバース工学科は、こうした未来のデジタル社会で活躍する人材を育成することを目的としています。
日本航空高等学校のメタバース工学科では、従来の航空業界における高度な技術教育に加えて、メタバースに関連する最新の技術や知識を学ぶカリキュラムを導入しています。
これにより、航空業界とデジタル技術の融合による新たな可能性を追求することや、自治体や企業と在校生が連携し、各自治体のメタバース空間を制作することで地方創生・地域活性化に寄与することなども期待されています。
学べる内容
メタバース工学科では、メタバース技術に関する基礎から応用まで幅広い分野での学びが提供されます。
FORTNITE、Cluster、Spatial、VRChat、Vket Cloudなど、国内外のメタバースプラットフォームを活用しながら、
具体的には、以下のような内容を3年間で学んでいきます。
- VRとARの技術
VRやARは、メタバースの構築に不可欠な技術です。メタバース工学科の学生は、VRシステムやARデバイスの仕組みを理解し、仮想空間内でのリアルな体験を提供する技術を学びます。これにより、仮想空間でのインタラクティブな環境設計やシミュレーションを行うスキルを習得できます。
特に、航空シミュレーションにおける活用も視野に入れて、航空技術とメタバース技術の融合を目指した学びが展開されます。
- 3Dモデリングとアバター制作
メタバース空間の構築には、リアルなオブジェクトやキャラクターを作成する3Dモデリング技術が重要です。メタバース工学科の学生は、専用のソフトウェアを使い、3Dモデリングやアバター制作の基礎を学びます。これにより、仮想空間内で使用される建物や環境、さらにはユーザーが操作するキャラクターのデザインが可能になります。
特に、航空業界での飛行機や空港施設など、リアルオブジェクトの再現技術を学ぶことも可能です。
- プログラミングとシステム開発
メタバースを運営するためのプラットフォームやシステムは、プログラミング技術を駆使して構築されます。
メタバース工学科では、学生は実際にUnity/Unreal Engineなどの専門ソフトを利用してプログラミング言語(C++やPythonなど)を学び、仮想空間でのインタラクションやシステム運用を自ら設計・実装する能力を養います。
これにより、学生たちはリアルタイムでのデータ処理や、ユーザー体験の最適化を可能にするスキルを習得することが可能となります。
- 人工知能(AI)と機械学習
メタバース内で自動的にユーザーとコミュニケーションを取ったり、状況に応じて最適な行動を取るAIキャラクターは、メタバース体験をより豊かにします。メタバース工学科の学生は、AIや機械学習の基本概念を学び、それをメタバース内で応用する方法を習得します。これにより、仮想空間内での自動化やインテリジェントなシステム開発が可能になります。
- データ解析と仮想経済
メタバース内での活動データや経済活動の管理は、仮想空間でのビジネスにおいて重要な要素です。メタバース工学科の学生は、データ解析の技術を学び、メタバース空間内でのユーザー行動データや仮想経済の運営を分析・改善するスキルを養います。また、仮想経済を活用したビジネスモデルの構築もカリキュラムに組み込まれており、ブロックチェーンやNFT技術など、経済学的視点からのメタバースの活用も学ぶことができるようになります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した学校は、これからメタバースの分野でキャリアを築きたいと考える学生たちにとって、最先端の技術を学ぶ絶好の環境であるのと同時に、卒業後にVR/AR開発やデジタルアート、ゲーム業界などで即戦力として活躍できる人材へと成長するための実践的な経験を積むことのできる、唯一無二の場所となるでしょう。
また、既存の教育機関でも、メタバースを教育手段として取り入れる学校は日に日に増えています。
今後の記事では、そうした教育内で取り入れられているメタバースの事例等も、順次ご紹介していく予定です。ご期待ください。
メタバースゲームに興味がある方はお気軽にご相談ください
こんな方におすすめ!
●メタバースゲームに興味はあるけれど、具体的な導入イメージがわかない…
●どのような活用方法があるのか知りたい
●費用感や導入の流れについて詳しく聞いてみたい
あなたのビジネスにメタバースゲームがどう活用できるのか、一緒に考えてみませんか?
初めて検討する方、興味があり情報収集をしたい方も大歓迎です。まずは お気軽にご相談ください。
▶オンライン相談へのお申し込みはこちら
